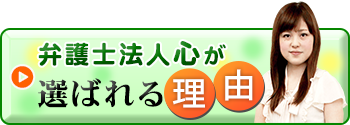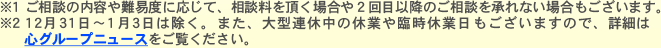遺言能力の判断基準
1 遺言能力の有無
遺言能力の有無について明確な判断基準を示すことは難しいです。
過去の事例では、以下で述べる事項を判断材料として、遺言能力の有無が判断されています。
ここでは、それぞれの判断材料について、具体的に説明を行いたいと思います。
⑴ 遺言者の精神状態
これは、遺言者が遺言時(相続開始時ではありません)に、どの程度の判断能力を有していたかです。
相続開始後に遺言能力の有無について争いが生じた場合には、どのようにして遺言時の遺言者の判断能力を証明するかが問題となることが多々あります。
公正証書遺言を作成した場合については、遺言を作成する際に、公証人が遺言者に対して発問するなどして、遺言者の判断能力について一応のチェックを行っています。
このため、相続開始後に遺言能力が問題となった場合に、しばしば公証人に遺言者の遺言時の様子を証言してもらうことがあります。
また、遺言者が生前に施設や病院を利用していた場合には、医師が長谷川式テストや判断能力についての診断を行っている場合があります。
これらの結果も、当時遺言者が有していた判断能力についての証拠となります。
さらに、生前遺言者のそばにいた相続人などが、遺言者の日常的な様子について証言することもあります。
例えば、遺言者が相続人の身の上相談にあずかっていたことを、遺言能力を肯定する一つの判断要素とした事例があります(大阪高判昭和60年12月11日家月39巻1号148頁)。
⑵ 遺言の作成経緯
遺言の作成経緯からいって、遺言者の短慮により遺言が作成されたおそれがある場合に、そのことを一つの判断要素として、遺言能力が否定されることがあります。
例えば、公正証書遺言で、遺言者が中等度ないし高度な認知症状態にあったこと、これまでほとんど深い付き合いがなく親族でもない第三者に遺産を遺贈する動機に乏しいことなどから、遺言能力を否定した事例があります(名古屋高判平成5年6月29日判時1473号62頁)。
⑶ 遺言内容
遺言内容が簡単なものであり、その意味内容を的確に認識することが困難ではない場合に、そのことを一つの判断要素として、遺言能力が肯定されることがあります。
反対に、遺言内容が複雑なものであることを考慮し、遺言能力が否定される例もあります。
例えば、遺言者が年齢に照らして標準的な判断能力を有していたこと、遺言内容が、全部で8か条に過ぎず、相続に関する者が妻や子、孫という近親者だけであり、相続財産が不動産と預金のみであることから、遺言能力を肯定した事例があります(東京高判平成10年8月26日判タ1002号247頁)。
他方、遺言者が高度の認知症であったこと、遺言書が、多数の不動産などの財産について複数の相続人に相続させるものであり、遺言執行者(被相続人の死後に遺言内容を実現する者)を項目ごとに2名に分けて指定し、1人の報酬について細かく料率を分けるものであるなど、複雑なものであったことから、遺言能力を否定した事例があります(横浜地判平成18年9月15日判タ1236号301頁)。
2 遺言能力についてのご相談
このように、遺言能力の有無については、様々な判断材料を総合的に考慮して判断がなされます。
そのため、一律に、「このような場合には遺言能力がある」と述べることは難しいです。
遺言能力の有無について争いがある場合は、弁護士にご相談いただけましたらと思います。