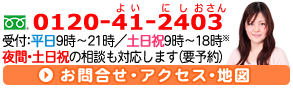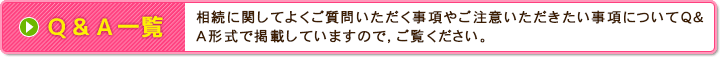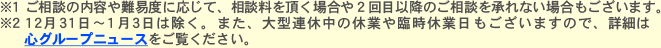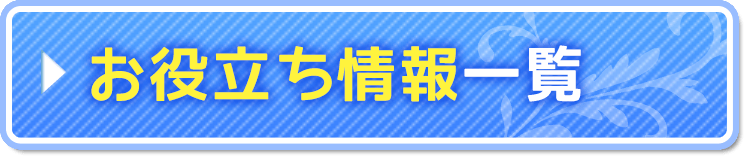相続税申告において贈与税の申告がされていない場合の対処
1 多額の贈与について、贈与税の申告、納付がなされていない場合
相続税申告の際、生前に被相続人から多額の贈与がなされているにもかかわらず、贈与税の申告、納付がなされていないと判明することがあります。
たとえば、相続税申告の資料をいただき、被相続人の預貯金の出入金の記録を確認すると、相続人に対して多額の送金がなされていることがあります。
そ相続人に事情を確認すると、実は、被相続人から相続人に対して多額の贈与がなされていたものの、贈与税の申告、納付がなされていないことが判明するというケースです。
贈与税の基礎控除は毎年110万円です。
つまり、ある年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の総額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
反対に、110万円を超える場合は、贈与税の申告を行い、贈与税を納付しなければなりません。
現実には、被相続人からの多額の生前贈与について贈与税の申告・納付がなされておらず、相続税を申告するといった段階でこのことが明らかになる事態が発生することがあります。
2 贈与税の問題を放置すると、どうなるのでしょうか?
このような場合には、贈与について何らかの対処を行わずに、相続税の申告だけを行えば良いのではないかと考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税申告を行う案件で贈与の問題を放置することは、おすすめできません。
相続税が課税される案件では、後日、税務署によって預貯金の出入金履歴の調査がなされる可能性があります。
そして、税務署は、相続人に対する多額の贈与が行われていることを把握すると、贈与税の課税がなされるべきとの判断を行う可能性があります。
こうなると、本来の贈与税だけではなく、加算税(令和5年までの贈与の場合、税務調査を受けるまでに申告した場合は50万円までは10%、50万円を超える部分は15%、税務調査を受けてから申告した場合は50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)や、延滞税(令和5年時点では、納期限の翌日から2か月間は年利2.4%、納期限の翌日から2か月経過後は年利8.7%)も納付しなければならなくなり、本来よりも多額の税負担を負うこととなってしまいます。
このような事態を避けるためにも、相続税申告に先立ち、または相続税申告と同時に、贈与税についても申告を行うことを検討すべきでしょう。
期限後であっても、自主的に贈与税の申告を行えば、加算税の税率を5%に抑えることができますし、延滞税が課税される期間も最小限に抑えることができます。
その結果として、課税される贈与税を、最小限の額に抑えることが可能になります。
3 どのような申告を行えば良いのでしょうか?
贈与の事実が判明した場合にどのような申告を行えば良いかは、贈与が行われた時期によって変わってきます。
贈与税の申告を行うべきかどうかだけでなく、相続税の課税対象になるかどうかも検討する必要があります。
この点については、2024年1月1日施行の法改正があり、相続発生日の7年前から相続発生日までになされた贈与については、さかのぼって相続税の課税対象とされることとなりました。
ただ、相続の発生時期、贈与の時期により、改正法の適用対象になるかどうかが異なっており、かなり分かりにくいです。
2024年1月1日以降に相続が発生した場合は、改正法の適用対象になるかどうかを、贈与ごとに、ルールを丁寧に当てはめて判断していく必要があります。
ここでは、たとえば、被相続人が2028年6月12日に亡くなったと仮定して、具体的にどのような申告を行えば良いかを説明したいと思います。
なお、相続時精算課税の届出については、なされていないものとします。
① 2023年12月31日以前になされた贈与
このような贈与については、贈与税の期限後申告のみを行います。
2023年12月31日以前になされた贈与については、改正法の適用対象にはならないため、今回のケースでは、相続税の課税対象にはなりません。
贈与税の本税についてのみ申告・納付を行うと、後日、税務署から、贈与税の加算税、延滞税についての納付書が届きますので、届き次第、加算税、延滞税の納付を行います。
以上のことから、贈与により生じる税負担は、㋐贈与財産額についての贈与税の本税、㋑贈与税の加算税、延滞税になります。
※ ただし、贈与税の申告期限(贈与の翌年の3月15日)から6年が経過している場合には、基本的には、贈与税は時効となりますので、このような場合には、贈与税の申告、納付は行いません。
② 2024年1月1日から、相続開始日の属する年の1月1日よりも前になされた贈与(2024年1月1日から2027年12月31日までになされた贈与)
このような贈与について、贈与税の期限後申告を行うこと等については、①と同じです。
①と違うのは、これらの贈与については、相続発生日からさかのぼって7年以内になされており、改正法の適用対象になりますので、相続税の課税対象にもなるということです。
まず、これらの贈与財産の額については、相続税の課税価格に加算して、相続税の申告を行わなければなりません。
ただし、相続発生日の7年前から相続発生日の3年前になされた贈与については、通算で100万円の非課税枠がありますので、贈与財産の額から100万円を差し引くことができます。
次に、期限後申告により納付された贈与税については、相続税から引き算することができます。
ただし、引き算の対象になる贈与税は、本税に限られます。
加算税、延滞税については、引き算の対象にはなりません。
以上のことから、贈与により生じる税負担は、差し引きの結果、㋐贈与財産額についての相続税、㋑贈与税の加算税、延滞税になります。
③ 相続開始日の属する年の1月1日以降になされた贈与(2028年1月1日以降になされた贈与)
このような贈与については、贈与税の申告期限(2029年3月15日)が未到来ですし、相続税のみが課税されることとなっていますので、贈与税の申告を行う必要はありません。
贈与財産額について、相続税の課税価格に加算して、相続税の申告を行わなければならないことについては、②と同じです。
ただし、贈与税の課税はありませんので、相続税からの引き算がなされることもありません。
以上のことから、贈与により生じる税負担は、㋐贈与財産額についての相続税のみになります。
4 贈与税が課税されない特例の適用を受けることはできますか?
贈与税については、特例の適用を受けることにより、贈与税が課税されないことがあります。
このような特例には、以下のものがあります。
・ 贈与税の配偶者控除
・ 直系尊属からの住宅取得資金の贈与
それでは、上記の①、②の場合で贈与税の期限後申告を行う際、これらの特例の適用を受け、贈与税が課税されないものとすることはできるのでしょうか。
結論としては、贈与税の期限後申告では、これらの特例の適用を受けることはできません。
これらの特例の適用を受けるには、贈与税の申告を期限内に行うことが条件となっているからです。
他方、上記③の場合については、贈与税の申告期限は到来していないわけですから、贈与税の申告期限(2029年3月15日)までに申告を行い、特例の適用を受けることとすれば、贈与税を非課税とすることができます。
そして、このようにして贈与税が非課税となった場合については、相続税のさかのぼっての贈与加算も行われないこととなります。
以上の結果として、贈与により生じる税負担は0円になります。
生前贈与についても遺留分を請求できるか 相続税の税務調査の流れ